←戻る
設定
レハト→親友以上を望み
ヴァイル→愛する人は心も近く
未分化。レハトが城に連れて来られてから半年が経過。
僕っこレハトが喋ります。
一応攻略対象(レハト抜)を五人登場させてみました。
幅が狭くて読みにくい方は Pixiv版 をどうぞ。
城下祭
「・・・レハト、レハト!」
レハトが一人中庭を歩いていると、自分を呼ぶ声がした。
少し警戒しつつ、声がしたであろう茂みの方へ近寄る。
とその時、レハトはビクッと震え、固まった。
茂みからにゅっと伸びてきた何者かの腕が、レハトを捕らえたのだ。抵抗する間もなくその腕に強く引き寄せられ、レハトは茂みの中へ引きずり込まれる。
血の気が引き、全身が強張る。
声をあげようと大きく息を吸い込むと、すぐに口を押さえられた。
「しっ!しーっ!レハト、落ち着いて!」
「・・・っ!?ああっ!・・・この、ばかイルっ!」
レハトは、茂みに引きずり込んだ犯人に向けて何度も拳を振り下ろす。
レハトを捕らえた腕の正体は、ヴァイルだったのだ。
「いててっ!ごめんごめん、そんなに怒んないでよ。」
「もうっ・・・び、びっくりしたあ・・・。」
そう呟いたレハトが震えていて、ヴァイルも事の重大さに気付く。
レハトも寵愛者であり候補者だ。冗談で済まされる行為ではない。
動揺したヴァイルが、慌てて謝罪と説明を始める。
「あああ!ほんとにごめんっ!怖かった?衣装部屋でいいこと聞いて。
すぐにレハトに教えたくて、抜け出してきちゃったから。・・・ご、ごめんなさっ・・・」
「だ、大丈夫だよ、ヴァイル。・・・それで、いいことって?」
「そう!衣装係の奴らが話してるのを聞いたんだ!
ね、レハト、あした暇?暇だよね?」
ヴァイルが興奮した面持ちで、レハトの手を握りながら尋ねる。
「う、うん。とくに用事はないけど・・・。」
「明日、城下で三年に一度の祭りがあるらしいんだ!どう?行ってみない?」
ヴァイルが一人高揚し、その勢いに少し引きつっていたレハトも、
祭りという言葉を聞いた途端、興奮し身を乗り出す。
「お祭りっ!?行くっ!行ってみたい!」
「よしきた!じゃ、さっそく、伯母さんとこにお願いに行こー!」
「ならぬ。」
そう一言で突き放したのは他でもない、リリアノだ。
「なんで?前は行かせてくれたじゃんか。」
「全く・・・。のう、お主ら、自らの立場を分かっておるのか?
成人までもうすぐだというのに、城下の祭りなぞ・・・
心中でも望んでおるのなら別だが。」
「そんなに心配なら大勢護衛を付ければ問題ないでしょ?
三年後にはどっちか王になってるんだし。もう二人で祭りなんていけないよ。」
ヴァイルが引き下がらないのを見て、リリアノは呆れたように深く溜息をつく。
「ふむ・・・そこまで行きたいと言うのなら、ヴァイル、お前だけならよかろう。
だが、レハト、お主はならぬ。」
「えっ・・・。」
リリアノの答えに、二人は唖然とし、黙り込む。
不意に訪れた静寂を破ったのは、レハトだった。
「どうして!? リリアノ、どうして僕だけ」
「・・・行こう、レハト。もう何を言っても無駄だよ。」
動揺し、リリアノを問い詰めようとするレハトをヴァイルが制して、
レハトの腕を引き、共に退場を促す。
レハトは不満を口にしながらも、大人しく謁見の間を後にする。
「譲歩した結果があの答えだったんだ。
絶対、あれ以上譲らないよ。いつもそうだもん。」
「・・・そっか。祭り、行きたかったな。」
「え、レハト、もう諦めちゃうの?俺に任せてよ、考えがあるんだ!」
ヴァイルがニヤッとして、レハトに耳打ちを始めた。
翌日、城門近くに祭りへと向かう鹿車が用意されていた。
レハトとヴァイルはあの後、それぞれ意見を出し合ったものの互いに言い分を譲らず、結局、口論となり仲違いしてしまったらしい。リリアノに事情を説明したヴァイルは、一人祭りに行く事を許され、至急手配されたのだ。
「本当によいのか。お主はレハトの事を少なからず思うておるのだろう。
このままお主が行くことで、溝が深まるやもしれぬぞ。」
鹿車の元に向かいながら、リリアノがヴァイルに言う。
ヴァイルは少し憤りを覚えたが、平然として答えた。
「そう思うなら一緒に祭りへ行かせてよ。駄目なくせにさ。
・・・せっかくのお祭りを、嫌な思い出で終わらせたくないし。
レハトが喜びそうなもの探して、仲直りするんだ!喧嘩になったのあんたのせいなんだから、
・・・上手く行かなかった時は力貸してよね。」
「ああ、よかろう。・・・存分に楽しんでくるがよい。」
ヴァイルの言葉に少し笑みを浮かべながら、リリアノが答えた。
その返事にヴァイルが何やらにんまりすると、祭りへ向かう鹿車に乗り込む。
ヴァイルに続いて、ヴァイルの侍従が鹿車に乗り込んだ。
そして、ヴァイルを乗せた鹿車は城を出て橋を渡り、城下の町へと消えていった。
リリアノは愛おしそうにその鹿車を見つめていたが、
待機していた護衛の者に、城内へ戻るよう促され、しぶしぶ踵を返した。
「これであやつを見るのは最後やもしれんのだ。
少しぐらい感傷に浸ってもよかろうに・・・。」
「・・・不吉なこと言わないでください。
ヴァイル様の護衛に選ばれたのは腕の立つ衛士ばかりです。
ご安心くださいませ。」
「ほう、なら我の警護は今」
手薄、と言いかけたところで衛士達が渋い顔をしているのに気付き、くくっと笑う。
「冗談だ、真に受けるでない。どれ、レハトの仏頂面でも拝みにいくとするか。」
そうしてリリアノがレハトの部屋に訪れると、レハトの侍従らしい女が出てきた。
リリアノの姿を見て、女侍従はぎょっとして慌てふためく。
「へ、へへへ、陛下っ!?あっあの、えっと、レハト様にご用でありますですかっ?」
慌てる女侍従の後ろから、落ち着いた様子で老侍従が出てきた。
女侍従はホッとした表情を見せると、陛下に一礼し部屋の奥へ下がった。
「リリアノ様。
レハト様は今中庭の市を楽しんでおられまして、部屋を留守にしております。
急ぎの用ならお呼びして参りますが、いかがいたしましょう。」
「おや、市に?一人でか?」
「はい。時折様子を見てはおりますが。
休日は極力一人で過ごしたいとのレハト様のご要望で、付き添いはしておりません。」
「ふむ。・・・ローニカよ。
話は変わるが、レハトの様子に何かおかしなところはなかったか?」
「・・・いえ、特には。私めにはいつものレハト様のように見受けられました。
休日ですし、機嫌も良かったように思われます。」
その答えにリリアノは何やらニヤけ始める。
「ほう?我はヴァイルからレハトと仲違いしたと聞かされたのだが、
機嫌がよかったのか、そうか。」
くくっと笑うリリアノに、ローニカと呼ばれた老侍従は怪訝な顔をする。
と、すぐに事態を悟り、顔に焦りが見えた。
「まさか。ヴァイル様と共に行かれたのですか?」
「いや?我はヴァイルしか見送っておらぬ。
部屋で拗ねておると思うて来たのだがな。
レハトは中庭の市に向かったのであろう?・・・っくく、あははは!」
リリアノが笑いを堪えきれず、その声が部屋に響く。
「ヴァイルめ、上手く行かなかった時は力貸せとは・・・このことか。
さすがは寵愛者というべきか。あやつなかなかやりおるな!」
声を上げて笑うリリアノに、ローニカは険しい顔をする。
「申し訳ございません。全て気付けなかった私めの失態でございます。
至急レハト様を連れ戻してまいります。」
そういってローニカが部屋を出ようとするも、リリアノが道をふさぐ。
「そう急ぐでない、ローニカよ。
まだレハトが城を出たと決まったわけではなかろう。まずは市を見てこい。
そして我に伝えよ。城外へ出るのはそれからだ、ローニカ。
我もお主のことが心配だからな。くくっ」
「お戯れを!」
「しっかり、探すのだぞ。」
リリアノは釘を刺すようにそう言うと、満足そうに部屋を後にする。
後ろ手を振りながら去っていくリリアノを見送ると、
ローニカは溜息をついて、レハトを探して市へと向かうのだった。
一方、ヴァイルを乗せた馬車は、順調に城下の町を走っていた。
小さな路地が入り組んでいる道に入ったとき、ヴァイルが荷に向けて話しかけた。
「そろそろいいんじゃない?レハト。」
その声を合図に、侍従が荷だと思っていたものが動き出し、
その中からレハトが出てきた。
ヴァイルと共に鹿車に乗っていた侍従がぎょっとする。
「レ、レハト様!?何故そこに!?抜け出して来られたのですか!」
侍従の叫びに近い大きな声に、鹿車が走りを止める。
何事かと中を確認した護衛達も目を丸くする。
一人だったはずの寵愛者が二人に増えているのだから当たり前だ。
鹿車に乗っていた侍従が外に出て、衛士達に説明し、話し合う。
「ど、どうするんです。引き返しますか?」
外で衛士達の慌てる声が聞こえる。
ヴァイルがレハトに合図を送り、レハトが頷くと、
同時に鹿車から外へ飛び出す。
驚いた衛士達を横目に、二手に分かれ狭い路地へと逃げ込んだ。
いきなり走り出た二人に、状況を把握できない護衛達だったが、
二人が路地に消えていくのを見て、事態を把握した一人が叫ぶ。
「なっ・・・何をしている!追いかけろ!連れ戻すんだ!」
そうして衛士と寵愛者の追いかけっこが始まったのだった。
路地を曲がりつつ、遠回りに鹿車が目指していたであろう方へ向けて走る。
当たり前だが、レハトは城下を歩いたことがない。
一応計画では、ヴァイルが近道になるよう走り、合流する手筈になっている。
さすがはヴァイル。曖昧すぎる計画だ。
・・・もし合流できなかったら、どうしよう。
不安を感じつつも、レハトはただひたすら走るしかなかった。
遠くで衛士達の声が聞こえる。
その時、不意に脇の路地から現れた何かと衝突した。
レハトは横に弾き飛ばされ、強く壁に叩きつけられる。
「いっ・・・たあ・・・」
「ご、ごごごめん!大丈夫?」
そう言ってレハトに手が差し伸べられる。
レハトは衝撃で朦朧とする視界の中で、その相手に目を凝らす。
「レ、レハト!」
「ヴァイル!よ、よかった・・・。」
双方がぶつかった正体を認識する。
差し伸べられた手を掴み、ヴァイルがレハトを引っ張り起こした。
「大丈夫?怪我してない?・・・走れる?」
「ちょっと擦りむいただけだよ。・・・うん、視界もはっきりしてきた。
大丈夫だよ、行こう!」
二人は手を繋ぎ、再び城下の町を駆け抜ける。
走り続けること数分、レハトは何かおいしそうな匂いがする事に気付いた。
「な、なんかいい匂いがしない!?」
「たぶん、お祭りの屋台だよ!てことは、もうすぐだ!」
そうして路地を抜けると、二人は屋台の裏に出た。
何か小さなパンのようなものが焼かれているようだ。甘い匂いがする。
屋台の主人が、突如として現れた息を荒らした二人に目を見張る。
そしてヴァイルの額を見て、寵愛者だということに気付き、
彼なりに状況を察したようだ。
「こりゃあびっくり!寵愛者様じゃあないですか。
何か事件でも?衛士様・・・は、呼んじゃ駄目みたいね。
すぐにお水を用意しますから、ちょいとお待ちを。」
屋台の主人がそういうと、飲み水の入れられたカップが二人に渡された。
「ふーっ、生き返った!ありがとね、おっさん。」
「あ、ありがとう。お兄さん。」
ヴァイルの発言に少し眉をひそめた主人だったが、
続けたレハトの一言に気をよくする。
「とんでもない、お礼なんて。
そうだ、ウチの商品お一ついかが?甘ーいお菓子ですよ。
でもま、庶民の食べ物ですから、二人のお口には合わないかな?」
そう差し出された丸いパンのような菓子を受け取り、
レハトはおどおどしながら少しかじる。
素朴な甘さで、なかなかおいしい。
横目でヴァイルを見ると、一口で食べきっていた。
「その食べっぷり、寵愛者様は食べたことがあるんですねえ。
お友達の方は、お祭りは初めてで?」
「? ああ、こいつも寵愛者だよ。ほら。」
ヴァイルはそう言って、レハトが額に巻いていた布を剥がした。
「ちょっ・・・やめてよ、ヴァイル!
人の多いところでは見せちゃだめだって、ローニカが・・・」
ヴァイルを牽制しつつ、レハトが慌てて布をくくり直す。
それを見ていた主人が、最初は目を丸くしたものの、納得したように頷いた。
「そういや半年ほど前に二人目の寵愛者様が現れたとか。
噂は本当だったんですねえ。」
「え、噂?」
「ええ。ま、貴族様と違って一般市民は城のことには疎いですから。」
リリアノがレハトは駄目だと言った理由がなんとなく分かった。
ヴァイルは日ごろの公務で、一般市民にもそれなりに顔が利く。
一方レハトは、中庭の市ですら簡単に紛れてしまうのだ。
額を隠していてはなおさらだ。
「・・・ねえレハト、もう一枚布持ってない?額に巻くやつ。」
ない、と首を振るレハトを見て、屋台の主人がそれなら、と
荷からフードの付いた子供用のコートを取り出す。
コートを取り出した時に、変なガラクタが一緒に地面に投げ出された。
「こいつで良ければ、お譲りしますよ。汚れたタオルよりマシでしょ?」
主人は調理油で汚れたタオルをヒラヒラさせながら言った。
「おお!おっさん、ありがと。一通り見て回ったら返しにくるよ!」
そう言うと受け取ったコートを羽織る。
少し大きいが、おかげで額は隠れた。
ヴァイルがくるくると羽織ったコートを確認するように回ると、レハトの手を取った。
「よし、行こうレハト!あ、俺お金持ってないから。レハトのおごりね。」
僕もそんなに・・・と言いながら、
レハトはヴァイルに引きずられるようにして外へ出る。
さっきまで気付かなかったが、中庭の市とは比べ物にならない程の店が並んでいる。
そして、何より未分化の子供が多い。中庭市ではあまり見かけなかった。
「わああ、凄いね、皆いきいきしてる!」
「城を抜け出してでも来た価値、ありそうでしょ?」
「うん、来てよかった!ヴァイル、連れてきてくれてありがとう!」
嬉しそうにはしゃぎ、ヴァイルに抱き付くレハト。
すると、ヴァイルが顔を赤らめる。
ヴァイルはサッと顔を背けると、そのままレハトの手を引いて喧噪の中に入った。
しばらく二人で祭りを満喫していた。
飴や綿菓子など、いろんなものを食べ歩き、遊戯も楽しんだ。
ふとレハトが辺りを見回すと、少し衛士が増えたような気がする。
一人の衛士が二人組の子供を引き留めては顔を顰めている。
間違いない、自分たちを探している。
「ヴァ、ヴァイル!衛士達が人混みの中で僕達を探してるみたい!」
「あ、やっと?ちょっと来るのが遅かったね、もう結構楽しめたし。」
「それは、ようございました。」
「わっ!」「ぐぇっ」
声と共に突如現れた人物によって吊らされ、二人の体が中に浮く。
「ロ、ローニカ!わあ、ごめんなさい!」
「あーあ、もうちょい遊びたかったなー。」
「リリアノ様を欺くとは・・・おかげで少し手間取りました。
二度とこんな真似はなさりませんように。
・・・ヴァイル様も少しは反省してください。」
「はいごめんなさいもうしません。」
もちろんヴァイルは棒読みだ。
こうして、レハトとヴァイルは日が暮れた頃、城に連れ戻された。
城に戻った二人を待ち受けていたのは、
リリアノと侍従頭による、五時間に及ぶお説教だった。
せわしなく続く小言の中、ヴァイルがこそこそとレハトに話しかける。
「ね、レハト。次の祭り、また、一緒に行かない?」
「え、次って三年後だよね?・・・さ、さすがに無理だよ。」
「んー・・・大丈夫だって。王になった方が許可すればいいのさ。」
「あ、そっか。・・・あれ、そうなの?」
「うん、いけるいける。
また小言を言われるのは避けられないけど。ふ、二人なら・・・。」
言いかけて、ヴァイルが顔を赤くする。
「・・・ね、約束。」
そして後ろ手で、ヴァイルとレハトは手を結んだ。
---end---
あとがき
三作目、初めて二次創作キットの追加シナリオ化させた作品です。そして、初めて一度に5人の攻略対象を出してみた作品でもあります。それぞれの特徴を掴んでそれを表すのは難しかったけど、書いてて楽しかった!
書いた本人がいうのもあれですが、一番好きなSSです。
各SSへの評価/コメント/アドバイス/誤字指摘、どれも嬉しいです!
評価はPixivの方へお願いします。
(Pixiv無料会員登録が必要。TwitterでもOK。)
Twitter ⇒ @riu_rante
PixivID ⇒
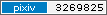
←戻る