←戻る
設定
タナッセ愛情B。
小さな街の屋敷にて二人で暮らしている。
レハトが喋ります。
幅が狭くて読みにくい方はPixiv版 をどうぞ。
岐路
屋敷の手狭な厨房。
使用人達が、いざ夕食の準備を始めようという頃。
そこには口を尖らせたレハトと、それをとても迷惑そうにしている使用人達がいた。
「今日は来客の予定もなく。外は頗る良い天気で。
なのに。なのに、タナッセってば。
書斎を片付ける、埃が舞って体に障るから入ってくるなって!」
そう言って、レハトが机に置いてあった布巾を手にバシバシと机を叩く。
・・・ここでも埃が舞っている。食事を準備しようというのに、非常に迷惑だ。
使用人達が頭を抱える中、一人が妙案を思いついた。
「レ、レハト様。ご夕食の前に、タナッセ様と外でお茶でもと誘ってみては?
お茶とお菓子をご用意しますが・・・いかがいたしましょう?」
成功したようだ。
振り回していた布巾が宙を舞い、レハトの瞳が輝く。
「わあ、それいいね。ありがとう、お願いしていい?」
「は、はい!至急ご用意いたしますね。」
使用人達が安堵の吐息をもらす。
なんとか準備に取りかかれそうだ。
「わっ!タナッセ! いい天気だよ。」
「・・・・・ああ。」
唐突に書斎の扉を開けたのは、すでに出かける準備を終えたレハト。
レハトの意図を汲み取ったタナッセが、とても厭そうにレハトを見る。
「・・・生憎だが。今日中に終えてしまいたいのでな。茶には行かんぞ。」
「えー!せっかく用意してもらったのに・・・っけほ!」
一応、窓は開けているが、黴臭くとても埃っぽい。思わずレハトが咳き込む。
だから言っただろう、とタナッセが呆れたように言う。
「ほら、体に障る。さっさと部屋から出て行け。」
タナッセがそう言って、叱叱とレハトを追い払おうとする。
しかし、大人しく引き下がるレハトではない。
強引に外へ連れ出そうと、レハトが部屋の中へ足を踏み入れる。
と、その時。
レハトが落ちていた本に足を引っ掛け、そのまま前のめりになる。
その手には、熱い紅茶と菓子の入った籠。
「なっ・・・!」
転びそうになるレハトをタナッセが駆け寄り既の所で支えると、
咄嗟に籠を壁に向けて弾いた。
「・・・っ!だ、大丈夫か?怪我はないか?」
「う、うん、ありがとう。そ、それよりも・・・」
レハトがタナッセの視線を先程弾いた籠に向けるよう促す。
そこには弾かれ落ちた衝撃で砕かれたティーポットと、
真新しい箱に入れられた、紅茶の琥珀色に染まった手紙の束があった。
あの手紙は。
「あ、あの手紙・・・ヤニエ伯爵の・・・?」
「・・・ああ、そうだ。・・・もともと、処分するつもりだった。お前が気にすることはない。」
タナッセの言葉に、レハトが胸を衝かれる。
嘘だ。間違いなく。
わざわざ新しく取り寄せた箱に入れて、処分するはずがない。
レハトの事を想って嘘を付いたのだろう。しかし。
・・・怒られた方が良かった、そう思った。
「・・・ごめん、なさい。」
「! お、おい、待て!」
レハトは謝ると、部屋を飛び出した。
タナッセの制止の声が聞こえたが、そのまま逃げるように屋敷を出たのだった。
「・・・何?レハトが帰ってきてない、だと?」
夕食時。使用人の慌てっぷりを見るに本当なのだろう。
タナッセは夕食までにはきちんと戻ってくるだろうと思っていたのだ。
彼は腐っても寵愛者。利用価値はいくらでもある。
・・・まさか。
タナッセの顔から血の気が引くのが分かる。
「タ、タナッセ様。」
使用人の声にハッとする。
不安を拭うように首を横に振った。
「もしかしたら入れ違いで帰ってくるかもしれん、お前は屋敷で帰りを待て。
私は探しに出る。・・・行くぞ、モル。」
タナッセはそう言ってコートを受け取ると、衛士を連れ外に出た。
今より数時間前のこと。
小さな丘の上。そこにレハトは寝転がっていた。
ここからはこの街の全景が見える。
「はあ・・・。」
レハトはため息をつくと寝返りを打った。
結婚し、城を出てからというもの、タナッセはレハトを叱らなくなった。
もちろん些細なことや照れ隠しで怒られることはある。
ただ本気で怒っているとき、それを言動で表すことがなくなったのだ。
もう二度と壊さぬように。彼なりの報いなのだろう。
彼は赦す。彼が赦したように。
それがタナッセ自身を苦しめ、レハトをも苦しめているとは知らず。
生まれたての赤ん坊のように。
壊れ物を扱うように。
「ん。ううん・・・?さ、さむ・・・。」
・・・気付けば、辺りはすでに暗くなっている。
レハトは未だ丘の上で寝転がっていた。
あまりにも心地がよくて、そのまま眠ってしまっていたのだ。
夕食の時間は疾うに過ぎているだろう。
「わわっ!い、急いで帰らなきゃ。」
震える身体を自らの手でぎゅっと抱きしめるように腕を組むと、立ち上がった。
そして、急ぎ足で屋敷へと戻る。
丘を下り街の門を潜ると、そこには見慣れた人影があった。タナッセだ。
彼もまたレハトに気付いたらしい。
タナッセがずんずんと大股でレハトに近寄る。
そして。
不意にレハトの視界が横へ向く。
寒さで頬がじんじんと痛む。いや、寒さだけではない。
タナッセを見ると、自らの手を押さえ今にも泣きだしそうな顔をしている。
・・・レハトは平手打ちを食わされたのだ。
「きっ・・・貴様・・・っ! 馬鹿だ馬鹿だとは思っていたが、ここまでとは!
それに!それに、なんだその・・・冷え切った、身体は。私への、当て付け、か・・・」
タナッセが息を詰まらせながらそう言うと、瞳から涙がこぼれる。
それは、レハトも同じだった。
タナッセはレハトが頬を押さえ涙を流しているのを見ると、本意ではないことを悟った。
タナッセがレハトに自分の着ていたコートを被せると、覆いかぶさる様に抱きしめる。
互いの瞳に安堵の色が滲んだ。
「あったかい。・・・ほっぺたいたい・・・。」
「・・・ああ、悪かった。だが、今回はお前が悪いだろう。」
「んー・・・ごめんなさい。」
謝ったレハトは、少し嬉しそうに微笑んでいた。
そうして二人は寄り添い、安閑と屋敷への岐路についた。
---end---
あとがき
五作目です。頬は痛いけれど、きちんと感情を剥き出してくれたタナッセにご満悦なレハト。
神業人業の起きた二人は、きっとこんな感じなんじゃないかな・・・。
レハトはそういう趣味がある・・・わけではないよ!
各SSへの評価/コメント/アドバイス/誤字指摘、どれも嬉しいです!
評価はPixivの方へお願いします。
(Pixiv無料会員登録が必要。TwitterでもOK。)
Twitter ⇒ @riu_rante
PixivID ⇒
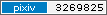
←戻る